

新しい“土木のカタチ”を創りあげたい。その想いのもとで同志が集い、
地場の建設会社たちがフラットな関係で、技術や人材といった資源を融通し合う。
いわば、“地域連合のゼネコン”として肩を組み、技術を磨き、市場を開拓していく―――。
それがマイスターエンジニアリンググループの〈土木カンパニー〉である。
私たち、地域の建設事業者が抱える課題はいろいろな方面に及ぶ。
「人材不足のために、仕事を請けられない。」
「繁閑の波が激しく、業績が安定しない。」
「採用もしたいが、社内基盤を整える余裕がない。」
そういった1社1社が抱える悩みに目を背けず正面から向き合い、
まずは情報共有をしながら信頼を築く。
そして各社の知見と技術といった強みを持ち寄り、
手を組むことで生まれる相乗効果によって、壁を乗り越える。
土木カンパニーが目指すのは、
社会にとっても社員にとっても幸せな未来づくりに挑んでいく、新しい組織。
誰からの依頼でもない。自分たち自らが進む道を切り拓く、これまでにない挑戦だ。

マイスターエンジニアリングは、1974 年の会社設立以来、日本の産業・社会インフラを支えている技術サービス集団。
このマイスターエンジニアリングが標榜する連邦経営の一翼を担うのが、2023年からスタートした、この土木カンパニーという組織である。
マイスターエンジニアリング社のグループ理論は、一般的にイメージするようなM&Aによる組織拡大とは異なる。
同社が“日本の超重要インフラ”と位置づける、日常生活や産業を支えるうえでの基盤となる分野の地位やイメージ向上をすることが真の狙い。
親会社・子会社といった無意味な上下の関係性をなくし、それぞれの会社がもつ個性や強みを失わずに、協業によって目的達成をめざす。



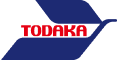
とだか建設 さいたま市
COMING
SOON

進幸技建 杉並区
COMING
SOON

泰平建設 横浜市
COMING
SOON

誠和光建 足立区
従業員数:64名売上:26億6100万円(どちらもM&A当時)
新卒でとだか建設に入社し、45歳で代表取締役社長へ就任。マイスターエンジニアリンググループへの加入当時のとだか建設の株主でもあり、創業家と共に成長戦略の一環として2021年にM&Aを実行する。現在は土木カンパニーの先導役として、社と社の垣根を超えた人材交流を促しながら、富田社長自身もグループ各社の若手社員の育成などへ積極的に取り組んでいる。

私がM&Aを検討したきっかけは、二代目の社長に就任して約5年経った頃。創業者である現会長が80歳を迎えるにあたり、創業家と共に会社の株式承継について真剣に考え始めました。当初は同族承継が前提でしたが、その先も続く相続税の課題や、今後も永続的にとだか建設を発展させていくことを第一に考え、たどり着いた答えが「他社に株を預ける」ことでした。
会長も元気ですし、「まずは一度、とだか建設の価値を確かめよう」と学びの一環として市場に出したところ、予想以上に多くの会社から申し出を頂きまして。その過程でマイスターエンジニアリングと出会い、意気投合。「M&Aは、同族経営の課題を解消すると同時に、会社が成長しながら新たな事業構想を実現するための、効果的な手段になりえる」と考えるようになったのです。
それまでは「同業である大手ゼネコンの傘下に入れば、工事の進め方や利益の上げ方などにおいて、自社のスタイルを貫くことは難しい。上下関係の力がことあるごとに働くのは目に見えている――。社員にとっても幸せな環境とは言い切れないだろう…」。こういった不安がありました。一方、マイスターエンジニアリングは異業種であり、グループに加わった会社の意志を尊重する〈連邦経営〉を実践している。この考え方に深く共感し、「この業務提携により、とだか建設の飛躍への道が開く」と確信したのです。

土木工事が減少していく中での経営の在り方、多様化する社員たちの働き方、地域社会への貢献の仕方。これらに対して、とだか建設1社だけで答えを見出すには限界がある。その壁を越えていけることこそが、マイスターエンジニアリンググループの一員となり、土木カンパニー発足によって生まれる最大のメリットだと考えます。
たとえば、働き方。若手社員に子どもが誕生したとします。もし仮にそのタイミングで本人から、「神奈川の実家へ戻りたい」という申し出があったとしましょう。当社がある埼玉まで通うのは負担が大きいですから、前もって横浜市のグループ会社の社長に相談のうえで出向させてもらう。それが叶えば、しっかり家族との時間を大切にできますしね。その後は向こうの会社でずっと働いてもいいし、とだか建設へ戻り、出向で身に付けた技術や経験を生かしてもいい。そういったいろいろな選択肢が増えました。
土木カンパニーとして連携することの意義は、そうした課題解決だけに留まりません。自社内のみでは狭くなりがちな議論や視野が、外部の人間とのコミュニケーションによっていい刺激となります。技術やノウハウを他社に教えたり学んだりすることは、自信や成長につながり、働くことの誇りも生む。これは現場の技術系社員に限らず、普段は会社の中から支える事務方も、他社に頼られる楽しさを感じています。また、多様化の進む各社の若手社員たちが交流し、刺激し合い、悩みや夢を語り合う機会がつくれるのは、未来の後継者育成にもつながっていくのではないか、そう感じています。

土木カンパニーは、東京23区をぐるりと囲むように隣接県の地域建設会社が組み、また23区内に拠点を構える会社とも連携することで「各社が自社の経営を優先しながら、首都圏のインフラ整備も担える」といった、これまでにない企業連合をめざしています。
先々に土木カンパニーとして、たとえ規模の大きなゼネコンと並ぶまでに成長したとしても、事業領域が異なっているため、無意味なバッティングはしない。中小企業ならではの使命であり、やりがいでもある、「地域への貢献」といった本質も薄れることはありません。
今はまだスタートしたばかりですが、この取り組みはやがて、これからの時代に適した“新しい土木事業者のカタチ”として認知されると信じています。とだか建設が旗振り役となり、土木建設業界に一石を投じたい。社員たちみんなが、自らの将来に期待しながら誇りをもって働き、それを見た若い人たちが次々に入職してくる業界に生まれ変わらせたい。そのためにも今は、この土木カンパニーの意義を示し、新しい仲間を迎えるために奔走しているところです。

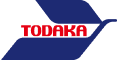
とだか建設 さいたま市
COMING
SOON

進幸技建 杉並区
COMING
SOON

泰平建設 横浜市
COMING
SOON

誠和光建 足立区